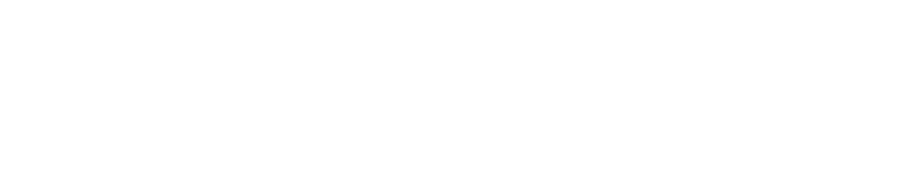PICK&UP No.55 石巻地区広域行政事務組合東松島消防署 -東松島市-
日常の“当たり前”を
防災・災害への備えにリンク!

いつ起こるか分からない、様々な災害。私たちが安心して日々を過ごすために知っておきたいことはまだまだたくさんあります。今回は東松島消防署 総務係、主査兼特別救助隊副隊長の岡田 啓さんに、災害への備えについて教えていただきました。
「備え」ってなんだろう
「防災グッズを準備する」「いざという時の避難経路を確認する」「災害に備える」———私たちは日常的に災害や防災に関する情報を自然と見聞きしています。
“災害”といっても、火災のような不注意や事故による人為災害、暴風 ・豪雨 ・地震 ・津波のような自然災害など様々な種類の災害があり、それらはいつ起こるか分からないもの。
私たちが当たり前に過ごしている“日常”が、いつ“非日常”になってしまうかは誰にも分かりません。だからこそ、その時がやってきてしまったときに少しでも日常を保つために“備え”は不可欠なのです。
知っていますか?
—ライフラインが途絶えたら—
災害時、ライフラインが途絶えてしまったら、私たちの生活はいったいどうなるのでしょうか?
電気が止まってしまったら、照明・冷暖房機器、テレビやインターネットが使えなくなり、体温調整や様々な情報の取得が難しくなります。水道が止まってしまったら、飲み水が確保できず、トイレやお風呂も使えないため衛生状態が悪化します。ガスが止まってしまったら、調理ができず、給湯器や暖房器具の使用も難しくなるため暖をとる手段が減ってしまいます。通信が断たれてしまったら、連絡がとれず、情報が得られない。公共交通機関が止まってしまったら移動ができない。何かしらの影響で道路が寸断されてしまったら、物流が途絶え食料や物品を手に入れることができない。——私たちの生活に欠かせないインフラ設備であるライフラインは、まさにその名のとおり『命綱』なのです。
では、ライフラインが途絶えてしまったときに備えて、“今できること”はなんでしょう?

「発災後ライフラインが9割程度復旧するまでの日数は、東日本大震災の時で電気は6日、水道は24日、ガスは34日かかりました。阪神淡路大震災の時で電気は2日、水道は37日、ガスは61日かかっています。災害の種類や規模によってもライフラインの復旧の程度は変わるので、季節や家族の人数 ・環境に合わせて持ち出しバッグ(防災グッズ等)の見直しや量の調整が必要になってきます。定期的に見直して入替をするやり方もありますが、私は日常的な備えとして『ローリングストック』をしています。」と岡田さん。
『ローリングストック』とは?
岡田さんが教えてくれた『ローリングストック』。皆さんは聞いたことはありますか?
ローリングストックとは、その名のとおり“備蓄した食品を日常的に消費し、食べた分を買い足していく”という循環型の備蓄方法です。
普段から食べているもの、飲んでいるもの、使っているもの——普段“防災グッズ・非常食”と認識していなくても、『食べ終わったから買い足す』という普段の生活の中で、自然と備蓄できているものもあるのです。それらを意識的に行うことが災害時に備える『ローリングストック』に繋がります。

岡田さんは「日常的に、当たり前にやっていることが防災・災害への備えにリンクしています。この時期だと水道からお湯を出すとき、始めに冷たい水が出ますよね。私はその水を溜めておいて、夜まで何もなければその水を植物にあげたり、加湿器に入れたりしています。これもローリングストックのひとつです。ガソリンも同様で、使ったら入れておくことを意識しておくといいですよ。食料や水などの備蓄品が揃っている場合、次に必要になってくるのは電気の確保。冬は毛布をたくさん用意したり、身を寄せ合ったりと電気やガスが途絶えてしまっても暖を取る方法がありますが、意外と大変なのは夏。電気が止まった直後であれば保冷剤などが使えますが、その後は体温調整や食料保存が難しく、衛生面も悪化しやすいです。夏は冬のように対策のしようがない—だからこそ車・ガソリンが十分な量あれば、季節に合わせた温度調整もできて、夜間の照明の確保はもちろん、必要に応じて移動も可能。発災後の対応の選択肢が広がります。」

無意識に対策バッチリ!
アウトドア好き・キャンパーに“備え”を習うべし
災害時、ライフラインが途絶えた状況を思い浮かべてみてください。
電気、ガス、水道——当たり前に使えていたものがない状況はとても不便です。
ですが、現代ではその不便さ・非日常を求め、大自然の中で不自由さを楽しむコンテンツとして、アウトドアが人気を集めています。その中のひとつ、キャンプに至ってはそもそもライフラインに依存しない環境で楽しむもの。火を起こし、暖をとり、調理をする——始まりの状況は違えど、その後の過ごし方としては災害時と同じ状況下となります。
岡田さんもアウトドア好きで休日はキャンプを楽しんでいるそう。
「キャンプで使うランタンや充電式のランプを普段から手の届くところに置いておいて、何かあったときにすぐ持てるようにしています。子どもたちとは“キャンプ体験”として、ライフラインに頼らない時間を設け、その状況をどう過ごすか考える機会を作っています。実際に体験することで“災害時に慌てない”という安心感が生まれます。キャンプに必要なものは災害時にも必要となるもの。アウトドアブームを防災と結び付け、“キャンプのスキルが災害時に活きる”ということを知っていただきたいです。」

今回は東松島消防署 総務係、主査兼特別救助隊副隊長の岡田 啓さんに、防災備蓄のこと、ライフラインが途絶えてしまったときのこと——“災害への備え”について教えていただきましたが、「日常的に、当たり前にやっていることが防災・災害への備えにリンクしている」という言葉がとても印象的でした。
『防災・備え=災害・非日常』とリンクしてしまうかと思いますが、この記事をきっかけに『防災・備え=日常の一部』とリンクできる方が増えていったら嬉しいです。
『備えあれば憂いなし』の言葉のとおり、 “もしものことを想定してしっかり準備しているから、何かあってもきっと大丈夫”。そのような状態を私たちの生活の当たり前にしていきたいですね。

東松島消防署では、防災について広く発信すべく様々な活動をされています。
石巻広域消防公式ホームページでは、消防のお仕事のこと、消防のQ&A(なんで消防車は赤で救急車は白なの?) 、119番のかけ方、応急手当WEB講習など様々な情報が掲載されています。ぜひチェックしてみてください。
◆石巻広域消防公式ホームページはこちら → http://isyoubou.jp/
石巻地区広域行政事務組合 東松島消防署
〒981-0504 東松島市小松字下浮足100番地5
TEL: 0225-82-2147
文・写真 酒井志帆